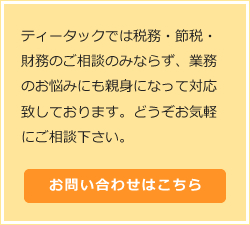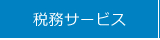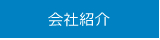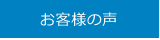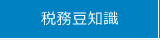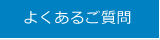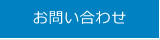- トップページ
- イマイのコラム 2025
- 非弁行為
非弁行為
2025/11/20
退職代行のモームリが警察庁の捜査を受けたという報道の中で、「非弁行為」という言葉が飛び交いました。
税理士として非弁行為が問題となるのは、相続税の申告において、亡くなった人の財産をどのように分けるのかという「遺産分割協議」の場です。税理士は弁護士ではないので、他人の財産を動かすことはできません。そのため、「このように分割しましょう」という提案はできません。
しかし、「A案で分割した場合には税金はこうなるけど、B案で分割した場合にはこうなります」というアドバイスをすることはできます。あくまでも、遺族(相続人)が分割内容を決めていただけないと、相続税の計算はできないということです。
「遺産分割協議書の作成を税理士が行う」ということがありますが、正確にはパソコンに入力し清書をしているだけで、作成者は遺族(相続人)です。ここは間違ってはいけない部分となります。
「非弁行為とは、(i)弁護士ではない者が、(ii)報酬を得る目的で、(iii)訴訟事件に加え、当事者間で既に紛争が発生している事案や、将来紛争が発生する可能性が高い(あるいはほぼ避けられないような)事案(「法律事件」)について、(iv)法律相談を行ったり、代理人として交渉を行ったりする行為(「法律事務」)を、(v)業とする(繰り返し行っている、あるいは初回であるとしても繰り返し行う予定で行う)ことをいいます。」(東京弁護士会ホームページより引用)
つまり、弁護士以外の人が、紛争が発生しているまたは紛争が発生しそうな事案について、相談を受けたり代理人として交渉を行ったらいけない…ということになります。法律知識のない人が専門家以外に相談することによって、不利な状況になることがないようにするのが目的です。税理士として非弁行為が問題となるのは、相続税の申告において、亡くなった人の財産をどのように分けるのかという「遺産分割協議」の場です。税理士は弁護士ではないので、他人の財産を動かすことはできません。そのため、「このように分割しましょう」という提案はできません。
しかし、「A案で分割した場合には税金はこうなるけど、B案で分割した場合にはこうなります」というアドバイスをすることはできます。あくまでも、遺族(相続人)が分割内容を決めていただけないと、相続税の計算はできないということです。
「遺産分割協議書の作成を税理士が行う」ということがありますが、正確にはパソコンに入力し清書をしているだけで、作成者は遺族(相続人)です。ここは間違ってはいけない部分となります。